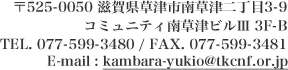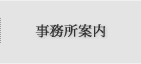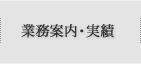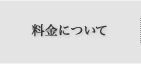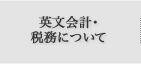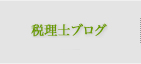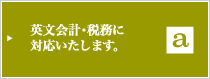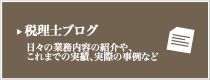日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
ジビエ料理 2019.01.21
先週土曜日、関与先さまの他士業の方と彼おすすめの和食店へ行ってきました。場所は京阪 唐橋前駅から瀬田の唐橋を渡ってすぐ(東詰)のところ。瀬田の唐橋は昼間たいてい渋滞しているので、車でほとんど通過することはないですが、夜に徒歩で唐橋を歩くと、遠くの灯りが川面に映ってなかなか風情がありました。ここ和食店『炭火割烹 蔓ききょう』は、ジビエ料理を出すことで有名で、「ジビエ」とは狩猟によって食材として捕獲された野生の鳥獣のこと。畜産との対比で使われることが多いそうです。とりあえず、スタートは焼野菜盛合せ(10種)から。それから、「酔っ払い蟹」こと・・せこ蟹のお酒漬けに鮒ずしは、店主が選んでくれた日本酒にもよく合います。

メインはメニューのジビエ料理の中から鹿肉の炭火焼きをいただき、最後の締めにカレーライス。ここは入荷があれば熊肉や鳩肉なども出すそうで、「厳選した素材をシンプルに炭焼きで」をポリシーにしています。

テーマ『相続税対策と事業承継税制等』 2019.01.14
今週ある公益財団法人にて、テーマ『相続税対策と事業承継税制等』のセミナーで1時間ほど講師をやります。内容は、まず生前贈与、生命保険の活用などオーソドックスな相続税対策を解説し、あと昨年4月に新設された「特例事業承継税制等」について概要を簡単に説明する予定で、レジュメも完成しました。
民法上は贈与について「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意志を示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法第549条(贈与))としています。なかには(贈与者が受贈者の)贈与税の申告および納付さえすれば、贈与が成立すると思われている方もおられます。贈与税の申告・納付は当然必要ですが、贈与(民法上の贈与)が成立するか否かの判断自体とは無関係です。加えて、年間の贈与額は110万円以下であれば申告は不要になります。やはり贈与者と受贈者が自署による贈与契約書を作成・保管し、受贈者が自身で通帳・届け出印・キャッシュカードを管理しておくことが重要です。
また、不動産を生前贈与する場合、贈与税の他に不動産取得税、登録免許税を考慮する必要があります。たとえば、固定資産税評価額2000万円の不動産(住宅)を贈与した場合、60万円(3%:住宅及び土地の取得で、商業ビル等の住宅以外の家屋は4%)および登録免許税40万円(2%)が納付(計100万円)になります。相続でしたら不動産取得税は不要、登録免許税のみ8万円(0.4%)ですので、これらも含めて生前贈与するか否か判断しなくてはいけません。
わたしのCD名盤 2019.01.07
昨年の後半は自家用車のオーディオが突然故障し、苦労しました。年末ディーラーは忙しく、そこから専門店へ出して修理するので、思いがけず時間がかかってしまった。なんとか昨年中に復活して一段落。現在はふたたび音楽の良さを実感している状態です。ちなみに、わたしがいつも聴いている音楽CDで、これは!と思うのはこの3枚で、まずお勧めするのはドナルド・フェイゲン『ナイトフライ』(1982年)。この人、ジャンルはロックの範疇に入るでしょうが、このCDはレゲエ、R&B、ラテン音楽、ジャズの要素を融合して、かつ洗練された作品になっています。あの桑田佳祐氏も音楽本の表紙で、このジャケットをオマージュしています。![DonaldFagen_TheNightfly[1]](http://kambara-office.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/DonaldFagen_TheNightfly1-285x285.jpg)
![518zAkEedyL._SX370_BO1,204,203,200_[1]](http://kambara-office.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/518zAkEedyL._SX370_BO1204203200_1-285x382.jpg)
あとは、ジャズピアニストのビル・エヴァンス『JazzHouse』(1969年)。彼はスローな名曲も多いですが、ここでは大好きな早弾きの曲がライブ録音されているのが嬉しい。それから「ボハ・ノヴァの女王」と呼ばれるアストラッド・ジルベルトのデビュー作『おいしい水』(1965年)は、スタンダード曲が満載でどなたでも聞きやすい内容になっています。いずれも古い作品ばかりですが、決してハズレはないと思うので、「温故知新」一度お聴きになってはいかがでしょうか。![IMG_5055[1]](http://kambara-office.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/IMG_50551.jpg)
![uccu-9202_wLk_extralarge[1]](http://kambara-office.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/uccu-9202_wLk_extralarge1-285x285.png)
紫野 今宮神社 2019.01.02
謹賀新年。みなさま明けましておめでとうございます。本年も引き続きよろしくお願いいたします。ことしは我々にとって大きな出来事であろう10月1日に消費税率引上げや軽減税率導入など控えていますが、まずは年明け早々から個人納税者の方々の年末調整(法定調書)や確定申告を手始めに、その後は平成30年度改正による新しい所得拡大促進税制や平成31年4月以降取得の設備投資への優遇税制などフォローしていければと思っています。
元旦は冬らしい寒さでしたが一日天気もよく、気持ちよく出かけることができました。ことしは恒例の墓参りのあと、京都市北区紫野にある「今宮神社」へ行ってきました。堀川北大路と千本北大路のあいだにある今宮門前の交差点を北に入ったつきあたりに朱色をした大きな楼門(写真左)があります。ここをくぐると向こう側に本殿(写真右)があり、すこし並びましたが無事に参拝することができました。
ここの愉しみは、祭事で用いられた竹やお供え餅を、参拝する人に厄除けとして提供したのが始まりとされる「あぶり餅」。時代劇に出てきそうな門前の参道にある2軒の店はそれぞれ1000年前(平安時代からあり、日本最古の和菓子屋)、江戸時代初期の創業と伝わっています。何年ぶりかで来ましたが、竹串で刺したお餅にきな粉をまぶして炭火で焼き(写真左)、白味噌だれをつけてたっぷりのお茶(写真右)といただきます。いつ食べても変わらない、どこかなつかしい味。2軒の店とも、元旦朝から大勢のお客さんで満員になっていました。

特定経営力向上設備等の範囲の「明確化」および「適正化」? 2018.12.24
約2か月前の日経新聞で『中小の投資減税延長』の見出しの記事がありました。2019年3月末で終了する中小企業の設備投資を促す税優遇措置を以降も延長するそうで、2019年4月以後にも設備投資を計画されている関与先さまもいらっしゃるので、ある程度は期待していましたが・・よかったぁという感想です。
そして、先週号「週刊税務通信」では、平成31年度税制改正大綱『中小企業経営強化税制は、特定経営力向上設備等範囲の明確化及び適正化を行った上、適用期限を2年間延長する』とありますが、この範囲の「明確化」および「適正化」とは、具体的にどのような設備等になるのでしょうか。従来のA類型とB類型のうちA類型のみ(工業会証明書入手)になったりするのか、それとも全く新しい基準が出てくるのか、すでに「経営力向上計画に係る認定」を受けていて実施期間中の場合は従来どおり「計画の変更に係る認定」でよいのかなど、早く方針が決定すればと思います。
一方、「新固定資産税特例」の場合、工業会証明書入手および経営革新等支援機関の事前確認が必要ですが、経営革新等支援業務を行う者としての認定を受けている私自身が「先端設備等導入計画に関する確認書」を雛形に沿って作成すればよく、確認書にある「認定支援機関ID番号」も近畿経済産業局に問い合わせれば教えてもらえます。近畿経済産業局の方のお話しでは、提出を受けた市区町村は「先端設備等導入計画に関する確認書」の提出した者が認定者であるかどうか確認をするとのこと。経営革新等支援業務の認定は、このようなところでも関与先さまの支援に役立つものと実感しました。
地鶏を堪能する 2018.12.18
きのうは事務所開設から本当にお世話になっている方と、JR瀬田駅ちかくの『地鶏炭焼 ばんさん』へ。まずは、いつものお造りの5種盛り(左から、ずり、もも、心臓、肝、むね)からスタートです。
税理士にとってIFRSとは 2018.12.10
2010年3月期から適用が始まった国際会計基準(IFRS)、日経新聞の記事によると、会計ルールを日本基準からIFRSに変更する企業が今年時点で200社を超えたそうです。これは昨年より2割増え、それら企業のグループ会社もIFRSを採用するとなると、税理士にとってもある程度の知識は押さえていく必要があるかもしれません。
以前、関与先さまの依頼で月次訪問時に数回にわたって、IFRSの概要を解説したことがありました。といっても、わたしもIFRSに接する機会はまだまだ限られているので、図解入りの入門書を使っての解説でしたが・・その印象はいまやっている税理士業務とは対極の会計ルールだなぁと改めて感じました。たとえば、IFRS採用でいちばん重要になるであろう「減価償却計算」に関しては、日本の税法では資産ごとにはっきり耐用年数が決まっていますが、IFRSでは「資産が企業によって利用可能と予想される期間をいう」とあります。つまり、耐用年数の決定は企業の観点から行うので、実態をみて判断する労力が出てきます。いずれにしても、まずは従来どおり日本基準で決算書を作成し、IFRSに基づいて必要な部分(減価償却計算、有給休暇引当金など)を変更していく・・というのがいちばん現実的な対応と思われます。
岩下 忠吾 先生 2018.12.06
昨日、近畿税理士会草津支部が主催する研修がホテルボストンプラザ草津びわ湖でありました。わたしは昨年から支部研修を担当しているので、研修ごとに他の会員の方とテーマや講師の決定など、打ち合わせをしながら進めていきます。決定した講師の先生についてはまず先生の事務所に電話して依頼し、それからもレジュメの編集や当日の段取りなど、講師先生と直接やりとりをしますが、著名な先生方と講演や書籍以外で接する機会ができ、今年に入って笹岡 宏保先生、金井 恵美子先生、坪多 晶子先生と、なかなか貴重な経験ができたと思っています。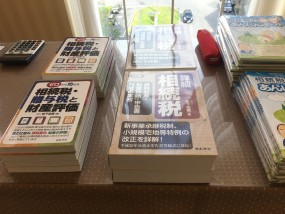
そして、昨日は東京税理士会より資産税や消費税などの多くの著書を出版されている岩下 忠吾先生をお迎えしました。テーマは『相続税の重要事項‐小規模宅地等の特例を中心に‐』。このテーマは支部会員からのリクエストによるものでしたが、快く応じてくれました。岩下先生は東京ことばでざっくばらんに、特にレジュメ以外で税制全般の話題も本音で話しされ、非常に興味深くお聞きすることができました。写真は研修受付に併設した書籍販売コーナーの風景です。
湖北と甲賀の紅葉めぐり 2018.11.26
週末金曜日、高島市マキノ町の「メタセコイヤ並木」へ行ってきました。自宅では晴天だったのが高島あたりから曇天になり、やがて現地に到着する頃には冷たい雨に。滋賀県でも湖北まで来ると日本海気候の影響を感じます。全長2.4kmにわたる約500本のメタセコイヤの並木道は「新・日本の街路樹百景」(読売新聞社)にも選定され、最近ではインスタ映えをねらって多くの方々が訪れる絶景ドライブルートになっています。

それから、翌日参加したゴルフコンペの帰りに立ち寄った「大池寺(だいちじ)」(甲賀市水口町名坂)。写真は、境内に続く入口の石塔と江戸時代初期の大名で茶人かつ作庭家である小堀遠州の作と伝えられる「蓬莱庭園」の様子。寺内には本堂・茶室・書院などがあり、それぞれ庭園から鑑賞できる赤色のモミジが美しい。こちらも、いま見ごろの紅葉をもとめて多くの観光客が訪れていました。

第8回みなくさまつり 2018.11.19
昨日(11月18日)開催された『第8回みなくさまつり』をご紹介いたします。サブタイトルは「~「えん」でつなぐ みなみくさつ~」。当日は10時~15時半まで南草津駅西口ロータリーから当事務所前を経て南草津二丁目交差点まで車両通行止になり、たくさんの飲食店や雑貨などのブースが立ち並びました。いくつかの企業や金融機関が協賛されていて、われわれ近畿税理士会草津支部も草津納税協会や草津税務署などの皆さんと西口近くにブースを構え、道行く人へ税の意識を高めていただくお手伝いをしました。写真にあるジュラルミンケースには1億円分の一万円紙幣(見本)が入っており、その重さを体験することができますが、実際試される人が多かったです。
また、ブースの中では「ちびっこぜいきんクイズ」として、こどもたちにクイズに答えてもらい景品を配りしました。例えば「問:国の財政を家計(月30万円)にたとえた場合、毎月いくらの借金(不足分)をすることになるでしょう? 答:16万円」のように、こどもたちにも国の財政事情を意識してもらい、税金の役割について少しでも理解してもらう内容になっています。