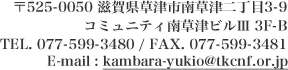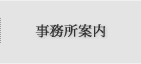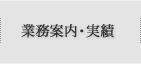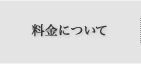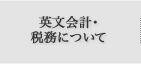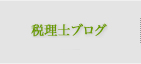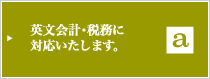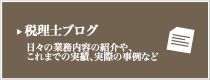日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
越境ECセミナーで講師 2017.04.24
先週21日(金)午後、コラボしが21にてTKC全国会海外支援研究会、中小機構で『海外展開支援セミナー~明日から使える 越境EC成功へのステップ』を開催しました。参加者は滋賀、京都、大阪の越境ECビジネスに興味のある企業や個人事業主の方々で、新聞社の大津支局からも取材に来られていました。
セミナーは3部構成で、まず株式会社プリンシプル(神戸市)の代表取締役 村田光俊さんが越境ECのビジネス全般についてお話しされます。この村田さんもご自身の商品をインターネットを通じて海外に販売されおり、その経験も生かして事業者向けに越境ECビジネスのコンサルティング事業を行っています。実際ビジネスを行った経験からお話しにも説得力があり、前職は大手コンサルティング会社におられたためレジュメの作り方も講演の仕方もプロ、若いですがなかなのものです。
つづいて、わたしが越境ECの税務会計の留意点について簡単に解説しました。主な内容として、① 売上計上基準は国内販売の出荷時点から、輸出販売は船積時点で計上すること、② 輸出取引の場合には消費税が輸出免税(消費税額 ゼロ)となるため、消費税申告により還付を受ける可能性があること、③ 取引通貨が日本円以外の場合、会計上為替差損益の認識するため為替リスクがあることなどです。
最後に㈱TKC関連会社のアイ・モバイル株式会社の方から、具体的なインターネットを使った海外向けのホームページの作成方法などの説明がありました。セミナー終了後、わたしも含めた講師した3名および㈱TKCの方 計4名で大津駅前の居酒屋で軽く反省会(?)をやり、うちお二人は東京からでせっかくなので滋賀の特産品・・お酒は松の司、料理は近江牛、鮒ずし(写真:左の小鉢)、赤こんにゃくなど・・を賞味していただき(なかなか好評でした)、無事セミナーを終えることができました。
『中小経営強化税制 設備取得後の経営力向上計画申請も容認』 2017.04.06
前回、ここで「平成29年4月1日以降の設備投資については、経営力向上計画を作成して経済産業局等に申請し認定を受けなければなりません。」と申し上げましたが、今週の週刊税務通信(No.3452)によると、「基本的には、いずれも(A類型、B類型)設備の取得前に同計画の申請・認定が必要となるが、①取得後60日以内に計画が「受理」され、かつ、②設備の「取得」と計画の「認定」が同一事業年度内であれば、設備の取得後の計画申請・認定も容認されることがわかった。」と、いわゆる弾力的な運用の具体的な内容が明らかになりました。これによって、設備の取得を計画の認定を待たずして行うことができ、中小企業にとって優遇税制をスムーズに適用できるものと思われます。
「経営力向上計画」の申請様式が変わりました! 2017.03.28
中小企業庁のホームページを見ると、『経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!(平成29年3月15日)』と大きく記載されています。
そのうち申請様式について言いますと、これまで生産性向上設備投資促進税制(A類型)は、工業会の仕様等証明書を申告書に添付(最低取得価額以上および平成29年3月31日までに取得等かつ事業の用に供することが前提)すれば適用を受けることができました。しかし、平成29年4月1日以降の設備投資については、経営力向上計画を作成して経済産業局等に申請し認定を受けなければなりません。
具体的には、① 経営力向上計画申請書(原本・写し各1部)② 工業会の仕様等証明書 ③ 経営力向上計画申請チェックシート ④返信用封筒(①、③は中小企業庁のホームページから入手できます。また、①は記載例(製造業)もあります)を各事業分野ごとの提出先に提出することになります。機械設備の取得は原則計画認定後になりますので、早めの申請が必要になります。
越境ECセミナーやります 2017.03.11
皆さん「越境EC」という用語はご存知でしょうか? この場合、ECとは“electronic commerce”のことで、直訳すると「電子商業」となりますが、一般にはインターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引ことをいいます。先週のニュースで、日本事業者の越境ECをサポートするサービスを提供しているイーベイ・ジャパン株式会社が、「越境ECの意向」に関する調査を実施したところ、国内EC運営者の67.2%は越境ECの出店に前向きに考えているという結果が出たそうです。また、大手企業も含め越境ECに対する抵抗度も年々薄らいでいる傾向にあるとも付け加えられていました。
そのようななか、TKC全国会海外展開支援研究会では、中小機構さんと4月から全国各地で『TKC・中小機構海外展開支援セミナー~明日から使える 越境EC成功へのステップ』を開催することになりました。内容は、「第1部:越境EC成功への10のポイント」、「第2部:越境ECの税務・会計の留意点」、「第3部:魅力あるHPの作成と運営のポイント」で構成され、滋賀県内では4月21日(金)午後1時半よりコラボしが21(3階中会議室)にて開催し、「第2部:越境ECの税務・会計の留意点」は私が講師を担当させていただきます。
特に、中小企業者が取り組む越境ECの現状を知りたい方、越境ECに取り組むにあたっての具体的なステップを知りたい方、越境ECの注意点・HPの活用方法など知りたい方にはお勧めです。せっかくの機会ですので、ご興味のある方はぜひご参加ください。(参加費無料/お問い合わせ先:TKC全国会海外展開支援研究会事務局 03-3266-9231)
苺 2017.03.03
今日午後、確定申告で自宅へお伺いした方から福岡県産の博多あまおう(イチゴ)をいただきました。先月も事務所に来ていただいた方から、同じくイチゴを・・良質なビタミンCは風邪気味の体に即効性があるのか、いくつか食べると不思議と風邪の症状が治まります。栄養はサプリメントより本来の食品より摂取すべき・・を実感しました。
中小機構SWBS 2017.02.20
中小機構では中小企業と支援機関とのマッチングを支援する「SWBS」という組織を立ち上げ、活動しています。その「SWBS」が開設しているホームページは「海外展開のパートナーを探す」「海外展開について相談する」「海外展開イベント・セミナー情報」など、いろいろな情報を収集することができます。
たとえば、新しい進出相談では、『みどりむしのサプリメントの販路拡大を検討しております。ターゲットになりうる国の情報などをご教授頂けますでしょうか。』『海外で梅酒の需要があれば進出を検討したいと考えています。助言いただける方を探しています。』など、多くの方がいろんな形で海外ビジネスを模索されているのがわかり参考になります。もし興味のある方がいらっしゃいましたら、こちらまで(https://swbs.smrj.go.jp/)ご検索ください。
『相続税対策の養子「有効」』 2017.02.06
2月1日付け日経新聞で『相続税対策の養子「有効」 最高裁初判断 縁組の意思尊重』の記事が掲載されていました。記事を読んでみると、被相続人が亡くなる前年に相続人である長男の息子(被相続人の孫)と養子縁組したことについて、他の相続人である長女と二女が「縁組は無効」と提訴したとのこと。
そもそも遺産分割の内容が縁組前とかわらなければ、養子縁組で遺産全体に対する相続税は減り、その無効を争った長女と二女にも税額低減のメリットはあったはず。これはあくまで推測ですが・・長男は息子の養子縁組によって、長男親子の相続財産を増加(法定相続分・・縁組前:長男のみ1/3 → 縁組後:長男1/4+孫1/4=1/2)させ(長女と二女の相続財産を減らされた)、争いになったとも考えられます。したがって、節税目的の養子縁組はあくまで遺産全体に対する相続税を低減するためとし、特定の相続人(養子縁組した相続人の親や配偶者および養子自身)の相続財産を増やすことは避け、また前もって他の相続人全員の了解と得ておくのが無難と考えられます。
今回の訴訟では、亡くなられた被相続人に縁組の意思があったか否かで争われました。それに対して最高裁は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘しています。ただ、死亡直前など明らかに縁組の意思が示すことができない状態で縁組されたものは、相続税法にある「相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合は、税務署長の判断で養子を算入せずに計算することができる」に該当し、縁組自体が無効にされる可能性もあります。
ゴッホ、ゴーギャン、ムンク 2017.01.23
先週末は名古屋の愛知県美術館で「ゴッホとゴーギャン展」を観に行ってきました。往きは、のんびり在来線で・・JR琵琶湖線米原駅から乗り換えJR東海道線に入ります。途中、左側に見える伊吹山の雪化粧が太陽光線に照らされとてもきれいでした。伊吹山だけでなく米原から大垣にかけては一面の銀世界で、やはり雪の多い地域であることを実感します。そうこうしているうちに、約2時間で名古屋駅、その後地下鉄2駅で最寄り駅の栄町に到着です。
このふたりの巨匠というかふたりの変人(?)は、フランス南部のアルルで共同生活をしていたことがあり、その時期の作品も多く展示されていました。ゴッホについてはそれ以前の作品や、ゴーギャンもその後タヒチへ渡って描いた作品も多数展示され、さすがに関心が高く午前から多くの方が鑑賞にこられていました。展示物は撮影禁止ですので、写真は出口の記念撮影コーナーでの一枚です。
これだけでも十分満足ですが、現在はムンクの絵画「イブセン『幽霊』からの一場面」も同時に展示(愛知県が5億5千万円で購入)されています。なにかの戯曲の一場面で、背景の色彩などはあの有名な「叫び」と共通するものがありました。(パネル下半分がその作品の写真)
十分堪能し美術館を出たところでお昼になりましたので、近くの「山本屋本店」で名物の味噌煮込みうどんを食べましたが、麺が固かったというか・・このことを麺にコシかあって・・と言うんですね。たいへんおいしくいただくことができました。
中小企業経営強化税制が創設されました 2017.01.16
今年3月末で「生産性向上設備投資促進税制」が終了しますが、平成29年度税制改正で新たに「中小企業経営強化税制」が創設されました。従来の「生産性向上設備投資促進税制」は優遇措置が50%特別償却か4%税額控除に対し、新しい「中小企業経営強化税制」では即時償却(100%特別償却)か7%または10%税額控除と、減税効果が拡大されています。
たとえば、1000万円の新たな対象資産を取得した場合、「中小企業経営強化税制」では、取得した事業年度に1000万円の減価償却費(従来500万円)計上か70万円または100万円(従来40万円)の税額控除が適用されることになります。
このような優遇税制は特別償却か税額控除の選択可能な場合が多いですが、特別償却は耐用年数にわたって計上する減価償却費を初年度にまとまって計上するだけで、その設備の耐用年数の期間で考えると変わらない。前述のケース(例:設備の耐用年数10年)で、初年度に減価償却費を1000万円計上するか、10年間にわたって1000万円計上するかの違いで10年間の税額への影響額は同じ。したがって、70万円の税額控除を選択した方が有利とも考えられますが、即時償却で1000万円の減価償却費を計上することにより、初年度は約330万円(=1000万円×実効税率33% > 70万円税額控除)の減税効果があり、実際には特別償却(即時償却)を選択するケースも少なくありません。業績が好調な状態が10年間継続するかわかりませんし、いまのうちにより大きな減税効果を享受しようという考え方もあります。
なお、新しい「中小企業経営強化税制」は、手続要件として「生産性向上設備投資促進税制」(B類型)であった投資計画を申請するほか、経営力向上計画も申請する必要あるなど、いくつかの手続きに違いもあり注意が必要です。
初詣で 2017.01.03
旧年中のご芳情を厚く御礼申し上げます。本年もよろしくお引き立てのほどお願いいたします。
元旦、二日と比較的おだやかで、よい天気がつづきました。ことしの初詣では元旦の朝から竜王町(綾戸)にある苗村神社へ行ってきました。国道から田園地帯の中の道をしばらく進むと、大きな森の横にひっそりとこの苗村神社があります。写真の西本殿は鎌倉時代の創建ということで国宝に指定されており、ありがたくお参りさせていただきました。
また、隣接する森の中にある東本殿(国の重要文化財)は、まだ朝も早く参拝者もいなかったので、なかなかおごそかな雰囲気をただよっています。この森には実際に多くの古墳が存在し、東苗村古墳群を名づけられています。
その後、車で約10分の三井アウトレットパーク竜王へ行きましたが、元旦早々非常にたくさんの人が来られてました。いくつもの福袋をかかえた人がいたりして、神社で味わった雰囲気とのギャップはなかなかおもしろかったです。それでは、みなさまにとってよい年でありますよう、今年もよろしくお願い申し上げます。